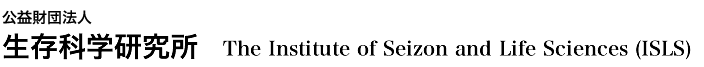出版物
「生存科学」誌への寄稿のお願い
1.生存科学36-1(2025)の特集テ-マ
- 特集1. 「倫理と生存」-生存科学とバイオエシックスとの関係からAIの倫理的側面や、安楽死まで-
-
「生存科学」次号(2026年2月刊行予定、36-1号)は、特集として、「倫理と生存」について取り上げることにいたしました。前号に引き続き、生存科学を取り巻く現代の課題について提起していくものです。「倫理と生存」にまつわる幅広い内容を期待致します。
故青木清先生(前生存科学研究所理事長)の追悼のため、過去の著作を検討した所、1976年の時点で、バイオエシックスが「生命倫理」か「生存科学」かという武見太郎との議論が紹介されていました。(参考 青木、2014)
その後、我が国では、生命倫理をはじめとして、様々な「倫理」が学術的、あるいは実務的に検討され、用語として定着しつつあります。(生命倫理 医療倫理 看護倫理 環境倫理 死生学 ;工学倫理、企業倫理、政治倫理)
今回の特集は、それらを統一するような「倫理」的な視点、すなわち、武見のいう「生存科学としての、バイオエシックスより広い意味の倫理・科学」を検討していきたいと思います。
このテーマの中で、AIの倫理的側面(バイオ、ナノ、インフォ)や、安楽死(尊厳死、死の問題として慎重に)といった、広義の倫理と生存に関わる個別テーマも一部含み込み、将来的な個別特集テーマへのとっかかりとしたいと思います。なお、情報文明や宗教・哲学などの課題も含むこととします。
以下、編集委員より
- 村上先生:
- 「幅の広い理念的な問題を取り上げるのは刺激的だが非常に難しい。しかし、一度きちんとやってみる価値は十分ある。」
- 丸井先生:
- 「武見太郎先生は『生存科学』という言葉で、当時のバイオエシックスとほぼ同じ内容を日本に紹介したかったのではないか。それが『生命倫理』という現場的な用語になったことには落胆があったかもしれない。もう一度『生存科学』を考える意味で、深みのあるテーマで面白い。」
- 大林先生:
- 「1975年のヘルシンキ宣言改訂に日本医師会がどう関わったか、また武見先生と青木先生の議論の根拠について興味がある。日本の生命倫理議論が『腰が定まっていない』と感じており、生存科学が今後、生命倫理や死の問題、安楽死問題も含めてどう考えていくかを明確にする上で、このテーマは重要。」
- 「倫理と生存」-生存科学とバイオエシックスとの関係からAIの倫理的側面や、安楽死まで-のテ-マの例
-
- 生存科学と生命倫理
- 生存科学と医療倫理、医療政策
- 生存科学と看護倫理
- 生存科学と環境倫理
- 生存科学と政治経済倫理
- 生存科学と死生学、安楽死問題
- 生存科学とケア、認知症
- 生存科学とAIの倫理的側面(バイオ、ナノ、インフォ)
- 生存科学と宗教、哲学
字数 5000~20000字
原稿締切り 2025年11月末
2026年2月刊予定 - 参考
- 生存の理法をめぐって―武見先生の人と思想―、青木清、江見康一、香川保一、小泉英明、生存科学 Vol. 14, A, p5-8, 2003.
- 「1976(昭和51)年の1月でしょうか。・・・バイオエシックスというのはどういうことかということ、医の倫理だけではなくて、新しく始まった生命科学、 DNA という分子生物学から始まった科学においても倫理が必要になったことを話しました。・・・『うん。僕もそれは考えてる。ただ、僕は、もう少し君より広い考えがあるんだ』と言われ、「生存科学」という『人間の生存を守る科学が必要なんだ」と、おっしゃられました。『バイオエシックスだと少し狭いんじゃないか。もう少し広い意味で、人間を科学的に理解し、人間の生存を守るということで、『生存科学』と言うのはどうかね』
- 青木清、生存科学をどう捉えるか、生存科学、Vol. 24 B, p18, 2014.
- 「アメリカのウィスコンシン大学の生化学者であったポッター(Van Rensselaer Potter) 教授が、初めて「バイオエシックス(Bioethics)」という言葉を使って本を出版しました。武見先生は、それをもう既に読まれていました。このタイトルは、やはり、環境と人との共存、人があって環境があるということです。その重要さについて説いていました。ですから、私が、『バイオエシックスというのを生命倫理ではどうでしょうか』と言ったら、武見先生は『そうかな』と言いました。バイオエシックスというのは、ライフサイエンスから来たものであると私は 認識してそう言ったのですけれども、もう少し広く考えたほうがいいのではないかというのが武見先生の意見でした。……これから人間が生存していくためには、それなりの科学的根拠に基づいたものが必要ではないかということを言われました。この生存の理法、つまり、理念としての科学を「生存科学」と言ったわけです。当時、日本としては、「生存」という言葉はあまり芳しいものではなかったです。……戦争中は、生き残れたということ自体がありがたかったわけです。戦後の栄養失調の中で生き残れたのです。私は、これが本当に生存かなと思いました。戦後、生存という言葉は、サバイバル、適者生存ということもあって、好まれない傾向がありました。生存というのは実はもっとすごくいい意味があるということを教えてもらいました。フランス語で「サバイバル」というのは、大変意味の深い、将来を見通すもので、人間の生存を守るためにあるということが、「生存」と言うのだと言われていました。バイオエシックスを突き詰めて考えていくと、この地球上にいる生物として、人間は人間が生かされている生物とともに生きていくということです。そうすると、一緒に、人間と他の生物がともに生存していく社会が必要なのだということになります。それでもいいと思いましたが、当時、私には、バイオエシックスを「生存科学」と言う勇気がありませんでした。それで、バイオエシックスを生命倫理というふうに日本語に訳していたわけです。」(松田 正己、生命科学、生命倫理と生存科学 青木清先生と生存科学研究所、生命と倫理(上智大学生命倫理研究所紀要) ,p9-17,2025-03-31) https://digital-archives.sophia.ac.jp/repository/view/repository/20250408103
- 特集2(連載)「生存科学の基本用語」
「生存の理法」、あるいは「生存科学」の定義には定まったものがないとされます。2024年に公益財団法人・生存科学研究所が設立40周年を迎えましたが、創設者(武見太郎)を直接には知らない世代が主となりつつある現在、「生存の理法」、あるいは「生存科学」に対する共通理解の構築が必要でしょう。また、そのためには、過去40年間で発展の著しい「生存科学」に関連する諸分野での用語の広がりや関係性を紐解いていくことも重要であると思われます。
武見太郎先生が活躍された時代(1950年代から80年代)に遡り、その社会背景や業績にも目配りが必要でしょうし、このような生存科学の基本用語に向けた取り組みは、私たちが生きてきた時代や社会、そして科学の功罪を理解する助けとなるでしょう。それらの取り組みを通して、今後の生存科学研究所の発展に向けた、世代や分野を超えた未来への架け橋となることを期待します。
第一回では、生命倫理とHIV/エイズを取り上げました。
以下にテ-マの案を示します。(参考 丸井英二「衛生学を入口にして生存科学を考える:生存学への試論」、生存科学34-2より)
- ① 「生存は単なる survival ではない」(生存とダーウィン流の「適者生存」、進化論の影響) 、古くからなじみのある「生存」
- ②個々の科学と学際的 (inter-disciplinary)、俯瞰的 (trans-disciplinary) な科学
- ③生命倫理との関連、bioethics = the science of survival という思想
- ④自然科学と社会科学(とくに経済学)、人文学との融合領域構想
- ⑤広い視野で「ライフサイエンス」をとらえなおす、ライフサイエンスというカタカナ語と「生命科学」、地球環境の危機、生態学(的視点)
- ⑥科学が還元論的に研究、遺伝子レベルでの研究、科学や技術の流れに危機感、統合的な視野の回復、カウンターカルチャと反科学
- ⑦研究が専門化され他の領域との関連を失う、個別の科学研究や技術開発
- ⑧人間としてではなく科学者や学者、研究者として生きていた人々
- ⑨科学者的であり、現場の医療の視点から日本社会や世界を
- ⑩bio- もまたlife と同じく「生命」に限定されない広い「生きている」ことを意味
- ⑪「生存の理法」は、「生」「存」「理」「法」の総合、「「学」よりは「道」のようなもの」
- ⑫「生存」の「生」は肉体的、精神的に融合し、倫理的、宗教的及び生物学的を内包した人生、「存」は、人間社会における多様なつながり、継承されていく実在的、総合的な存在。生存の「生」あるいは「生存」そのもの
- ⑬「理法」の「理」は科学的、人間を超えた自然の事理、「法」は人間社会で長年形成されてきたルール、精神的支柱
- ⑭同一性の維持と種の保存、人生としての「生存」
- ⑮「生きものは開放系として自己同一性を保ち、増殖して後続世代をつくっていく」
- ⑯私たち人類の well-being が求められ、個人から人びとへ拡張し、「あるべき、よき生存」であり、 better life が「よりよき生存」、生存は life であり being
- ⑰生存は生命であり、生活、人生、よりよい生を保証するのは生産であり、政治経済学
- ⑱「生存」に進化論的な抵抗感に逆らって、白紙の「生存」概念を、「生存科学」とする
- ⑲「生存科学」が「分けられた個別科学」としてではなく、階層が一つ上の統合的なメタ科学、生存科学の定義はむずかしい、「生存科学」が定義を許さないレベル
- ⑳個別の科学が吸収されるブラックホール、専門分科を前提とした各種科学を要素とした全体システムとしての「生存学」とよぶ日本語言語空間
字数 1000~10000字
原稿締切り 2025年11月末
2026年2月刊予定
特集の他に、独自の研究論文、提言や報告などを期待しております。また研究会メンバーの方々にも研究成果の投稿をお勧めいただければ幸いです。(投稿規定は近々、変更予定です。) ご執筆のご予定、並びにテーマ(仮題)をメール等で7月20日までにお返事いただきたく、ご協力、ご支援のほど、重ねてお願い申し上げます。
2025年6月
生存科学研究所理事長 松下 正明
「生存科学」編集責任者 松田 正己